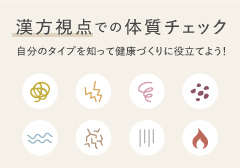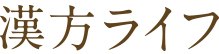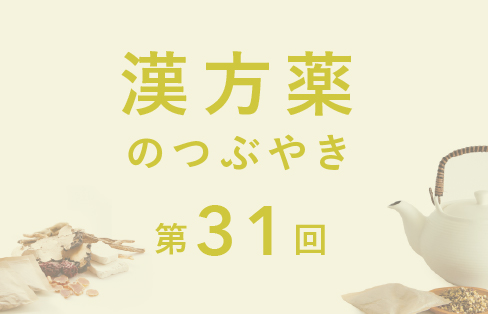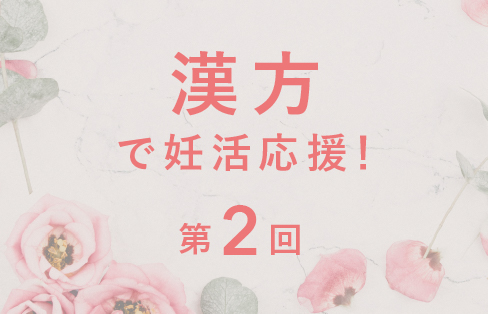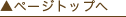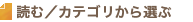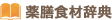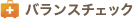- 鈴木 養平 - Youhei Suzuki[薬日本堂漢方スクール講師・薬剤師]
1969年宮城県生まれ。東北医科薬科大学卒業後、薬日本堂入社。臨床を経験し、店舗運営、教育、調剤、広報販促に携わる。札幌に勤務中、TVの漢方コーナーにてレギュラー出演。漢方薬による体質改善の指導・研究にあたる一方で、“漢方をより身近に”とセミナー講師・雑誌・本の監修(『おうちでできる漢方ごはん』『かんたん・おいしい薬膳レシピ』)で活躍中
漢方スクールでの担当コース・セミナーはこちら
Instagramはこちら
「しあわせは食べて寝て待て」から学ぶ“ゆる薬膳”②
プチ不調は自分でカイゼン Vol.74
体に合った食材を食べておけば、次の季節健やかに過ごせる
これは第7話で司さんが話した言葉です。
毎日食べる食事に、季節や体調に合わせた食材を取り入れてみる。
そうした“今”の心がけは、「次の季節を健やかに過ごすための準備である」と考えましょう。
見返りを期待せず、「未来の自分のためのセルフケア」と考えると毎日の食材選びも楽しくなりますね。
季節と五臓、そして食材の色との関連をまとめました。
五臓とは身体の機能を5つに分類した考え方で、肝(かん)心(しん)脾(ひ)肺(はい)腎(じん)のことを言います。
春 肝(気のめぐり、血の貯蔵) 香りのある青食材で気を巡らせる
夏(梅雨) 心脾(意識、消化) 赤食材で血をつくり、黄色食材で元気をつくる
秋 肺(呼吸、皮膚) 白食材で潤いをつくる
冬 腎(老化、生殖) 黒食材でからだをきれいにする
色にちなんだ代表的な食材
五色の食材を満遍なく食べると五臓が喜ぶと言われています。
また、季節によって乱れやすい五臓があり、それに対応する色の食材をとると五臓が喜びます。
春は肝が乱れやすく、肝が乱れてイライラするときは、香りがある青食材がおススメ
セロリ、春菊、パセリ、三つ葉、シソの葉、パクチーなど

夏は心と脾が乱れやすく、心が乱れて不安や不眠ぎみの時は赤食材、脾が乱れて元気がないときは黄色食材がおススメ
人参、レバー、ナツメなど
トウモロコシ、はちみつ、かぼちゃ、大豆など

秋は肺が乱れやすく、肺が乱れて咽のイガイガ、皮膚のカサカサの時は白食材がおススメ
白きくらげ、白ゴマ、松の実、大根、レンコンなど

冬は腎が乱れやすく、腎が乱れて老化が進んでいる時は、黒食材がおススメ
黒きくらげ、黒ゴマ、黒豆、黒酢、シイタケ、ヒジキなど

他にもある、ゆる薬膳の考え方
食材には五味があると薬膳では考えます。
味によって働きがあり、その働きを期待して食材をとることで身体を整えます。
酸味 ひきしめる(多汗、頻尿など) 梅、レモン、酢など
苦味 熱を,冷ます(イライラ、充血など) ゴーヤ、緑茶、菊花など
甘味 滋養強壮(疲れ、だるさなど) カボチャ、トウモロコシ、ナツメなど
辛味 発散・巡り(かぜ予防など) シソ、生姜、ネギなど
塩味(鹹) 柔らかくする(しこり、便など) 昆布、海藻など
スポーツをして汗をかいたときのハチミツ(甘)レモン(酸)は、汗を止めて元気をつけてくれるので理にかなっていますね。
また、酸味と甘みの組み合わせは、体の潤いを作り出すと言われており、消耗した体液づくりにもなるのでおススメです。
黒豆でむくみとだるさ対策
4話の最後に、さとこがチリコンカンを作っていましたね。
「黒豆は、だるさを取ってくれるから・・・」と最後に黒豆を入れていました。

黒豆は、黒い食材の代表格。黒食材は腎にいいとされています。
平 甘 脾肝腎
利水 水巡りを良くしてむくみに良い
益腎、解毒 老化を遅らせ、きれいにする
活血 血行をよくする
滋陰補血 潤いをつくる
働きをみてもスーパーフードですね。普段のお茶を黒豆茶に変えてみたり、おやつを炒り黒豆をポリポリ食べるなど、気軽に取り入れやすい素材なのでおススメです。
-
全国から承っております
オンライン漢方相談(無料)を
ご希望の方へ -
漢方ライフを運営する薬日本堂では、店舗へご来店いただかなくても、スマホやPCを使用してオンライン漢方相談を受けられます。薬剤師をはじめとした漢方の専門家がお客様のお悩み(ダイエット、不妊など)や症状、体質、生活習慣等をお伺いした上で、お客様にあった漢方薬・商品をご提案し、根本改善のための生活習慣のアドバイスをいたします。
-
おすすめ情報
漢方の資格取得に興味のある方必見
-
漢方を学べる【薬日本堂漢方スクール】はご存じですか?漢方と養生を学んで取得できる「漢方養生指導士」の資格は、ご自身やご家族の健康管理に活かせる注目の資格です。
「漢方スクールってどんなところ?」「どんなことが学べるの?」など、漢方スクールの魅力を人気講師・鈴木養平先生が無料動画で徹底解説します!
-
気軽に漢方を楽しもう
はじめての方にもわかる「漢方・薬膳」セミナー
-
漢方ライフを運営する薬日本堂では、はじめての方にもわかる「漢方・薬膳」セミナーを開催しております。1回完結型のワンデイセミナーですので、はじめて漢方を学ぶ方にオススメです。様々なセミナーが開催されています。オンラインで受講できるセミナーも豊富にございますので、ぜひお気軽にご参加ください。


この記事が気に入ったら
いいね!しよう
最新情報をお届けします
前の記事
-
全国から承っております
オンライン漢方相談(無料)を
ご希望の方へ -
漢方ライフを運営する薬日本堂では、店舗へご来店いただかなくても、スマホやPCを使用してオンライン漢方相談を受けられます。薬剤師をはじめとした漢方の専門家がお客様のお悩み(ダイエット、不妊など)や症状、体質、生活習慣等をお伺いした上で、お客様にあった漢方薬・商品をご提案し、根本改善のための生活習慣のアドバイスをいたします。
-
おすすめ情報
漢方の資格取得に興味のある方必見
-
漢方を学べる【薬日本堂漢方スクール】はご存じですか?漢方と養生を学んで取得できる「漢方養生指導士」の資格は、ご自身やご家族の健康管理に活かせる注目の資格です。
「漢方スクールってどんなところ?」「どんなことが学べるの?」など、漢方スクールの魅力を人気講師・鈴木養平先生が無料動画で徹底解説します!
-
気軽に漢方を楽しもう
はじめての方にもわかる「漢方・薬膳」セミナー
-
漢方ライフを運営する薬日本堂では、はじめての方にもわかる「漢方・薬膳」セミナーを開催しております。1回完結型のワンデイセミナーですので、はじめて漢方を学ぶ方にオススメです。様々なセミナーが開催されています。オンラインで受講できるセミナーも豊富にございますので、ぜひお気軽にご参加ください。