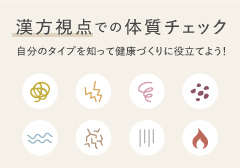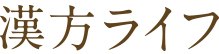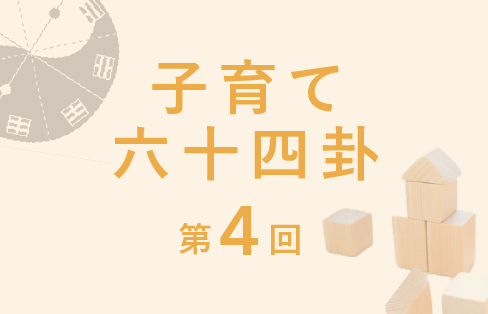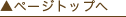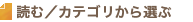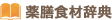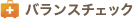- 鈴木 養平 - Youhei Suzuki[薬日本堂漢方スクール講師・薬剤師]
1969年宮城県生まれ。東北医科薬科大学卒業後、薬日本堂入社。臨床を経験し、店舗運営、教育、調剤、広報販促に携わる。札幌に勤務中、TVの漢方コーナーにてレギュラー出演。漢方薬による体質改善の指導・研究にあたる一方で、“漢方をより身近に”とセミナー講師・雑誌・本の監修(『おうちでできる漢方ごはん』『かんたん・おいしい薬膳レシピ』)で活躍中
漢方スクールでの担当コース・セミナーはこちら
Instagramはこちら
からだの根本を整える~冬への準備と腎養生
プチ不調は自分でカイゼン Vol.79
季節と腎の関係は!?
11月7日に立冬を迎えます。
空気は冷えて日も短くなるように身体も冬モードに変化していきます。
漢方でいう「腎(じん)」は、生命力の源である「精(せい)」を蓄え、成長・生殖・老化・水分代謝など、からだの根本を支えています。腎の働きが弱まると、冷え・腰痛・疲労感・むくみ・白髪・耳鳴りなどがあらわれやすくなります。
冬の寒さに一番影響を受けるのが「腎」になるので、冬に備えるなら、この時期からの腎ケアが重要です。

●あなたの腎元気度チェック
次の項目に当てはまるものはいくつありますか?
☐ 朝起きるのがつらい/疲れが抜けにくい
☐ 足腰が冷える/腰が重だるい
☐ 夜中にトイレが近い/むくみやすい
☐ 髪のパサつきや白髪が気になる
☐ 耳鳴りやめまいを感じる
☐ のどや肌が乾燥しやすい
☐ 寒くなると気分が沈みがち
2~3個は軽い腎疲れ、5個以上はしっかり養生が必要なサインです。
暮らしで出来る腎の養生
●腎を養うのは「黒」と「根」の食材
黒豆、黒ごま、ひじき、昆布、わかめ、山芋、くるみなどが腎を補うおすすめ食材です。
レンコン、サトイモ、サツマイモなどの根菜は体を内側から温め、煮物やスープで取り入れるのがおすすめ。
辛みは、発散の働きと気血の巡りを良くする働きがあるので、生姜やニンニク、ネギ、コショウ、シナモン、唐辛子などを意識して料理に加えるのがおすすめです。
●静かに体を整える習慣を持つこと
・首・手首・足首・腰・おなかを冷やさない。
冷えてから温めるでは遅いです。特に足首を冷やさないように、朝起きたらまずは靴下!を心がけて下さい。
また、外出時は首の後ろにカイロを貼るようにしましょう
・夜は湯船でゆっくり温まる(ぬるめ41℃前後)
就寝時間の1.5~2時間前を目安に入浴をします。好きな香りがする入浴剤もおすすめです。
入浴後は、部屋の明かりを暗くしてゆったりとした自分中心の癒し時間にしてください。
・深呼吸や早めの就寝で腎を休ませる
日が短くなるということは、活動時間を少なくするということ。
決して無理をせず、休みことを優先する心がけが必要です。しっかり休むことができれば活動効率も上がってきますよ。
耳マッサージで腎を整える
耳には全身の臓腑とつながるツボが集まっており、簡単なマッサージで腎の働きを整えることができます。朝すっきり起きられない時、デスクワークで疲れた時などに行うと、疲労回復の効果があります。

●基本の耳マッサージ法
①耳全体のマッサージ
初めに両手の手のひらで耳をおおい、上下にゆっくり5 ~ 6 回こすります。
②耳をつまんでひっぱる
次いで、親指と人さし指で耳をつまんで上の方から順序よく、1 ヶ所を5 ~ 10 回リズミカルに、ゆっくり軽く、次第に速く強く引っぱります。
③耳をひねる
終わりに、軽く手を握るようにして、親指とゲンコツで耳全体をはさみ、前後に5 ~ 6 回ひねります。
このマッサージを入浴後や寝る前に行うと、血流が促され、冷えや疲労感の緩和、腎の働きのサポートにつながります。
11月は冬に向けて体の“根っこ”を育てる季節。
温める・潤す・補う・整える――食事や生活習慣、耳マッサージなど、無理のない方法で少しずつ整えることが、冬を健やかに過ごす秘訣です。
腎をいたわり、季節のリズムに寄り添う暮らしを楽しんでみてください!
-
全国から承っております
オンライン漢方相談(無料)を
ご希望の方へ -
漢方ライフを運営する薬日本堂では、店舗へご来店いただかなくても、スマホやPCを使用してオンライン漢方相談を受けられます。薬剤師をはじめとした漢方の専門家がお客様のお悩み(ダイエット、不妊など)や症状、体質、生活習慣等をお伺いした上で、お客様にあった漢方薬・商品をご提案し、根本改善のための生活習慣のアドバイスをいたします。
-
おすすめ情報
漢方の資格取得に興味のある方必見
-
漢方を学べる【薬日本堂漢方スクール】はご存じですか?漢方と養生を学んで取得できる「漢方養生指導士」の資格は、ご自身やご家族の健康管理に活かせる注目の資格です。
「漢方スクールってどんなところ?」「どんなことが学べるの?」など、漢方スクールの魅力を人気講師・鈴木養平先生が無料動画で徹底解説します!
-
気軽に漢方を楽しもう
はじめての方にもわかる「漢方・薬膳」セミナー
-
漢方ライフを運営する薬日本堂では、はじめての方にもわかる「漢方・薬膳」セミナーを開催しております。1回完結型のワンデイセミナーですので、はじめて漢方を学ぶ方にオススメです。様々なセミナーが開催されています。オンラインで受講できるセミナーも豊富にございますので、ぜひお気軽にご参加ください。


この記事が気に入ったら
いいね!しよう
最新情報をお届けします
前の記事
次の記事
-
全国から承っております
オンライン漢方相談(無料)を
ご希望の方へ -
漢方ライフを運営する薬日本堂では、店舗へご来店いただかなくても、スマホやPCを使用してオンライン漢方相談を受けられます。薬剤師をはじめとした漢方の専門家がお客様のお悩み(ダイエット、不妊など)や症状、体質、生活習慣等をお伺いした上で、お客様にあった漢方薬・商品をご提案し、根本改善のための生活習慣のアドバイスをいたします。
-
おすすめ情報
漢方の資格取得に興味のある方必見
-
漢方を学べる【薬日本堂漢方スクール】はご存じですか?漢方と養生を学んで取得できる「漢方養生指導士」の資格は、ご自身やご家族の健康管理に活かせる注目の資格です。
「漢方スクールってどんなところ?」「どんなことが学べるの?」など、漢方スクールの魅力を人気講師・鈴木養平先生が無料動画で徹底解説します!
-
気軽に漢方を楽しもう
はじめての方にもわかる「漢方・薬膳」セミナー
-
漢方ライフを運営する薬日本堂では、はじめての方にもわかる「漢方・薬膳」セミナーを開催しております。1回完結型のワンデイセミナーですので、はじめて漢方を学ぶ方にオススメです。様々なセミナーが開催されています。オンラインで受講できるセミナーも豊富にございますので、ぜひお気軽にご参加ください。